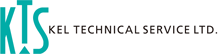KTS's POV KTS's Point of View
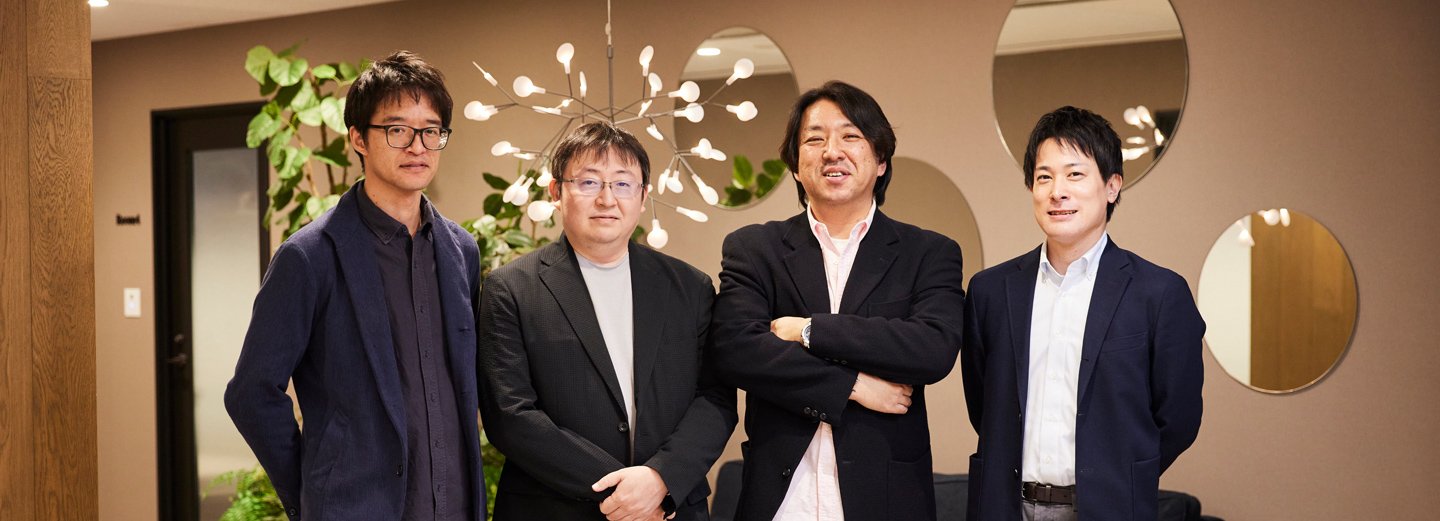
お客様、協力会社、社内。
どこのコミュニケーションも
怠らないから、
いいプロジェクトになる。
IaaSサービス用新基盤構築
プロジェクト座談会
MEMBER
-

M.N
- PROFILE
- 2016年KELからの転籍という形でKTS入社。普段はPMとしてプロジェクト管理を担当する他、メインフレーム案件では設計・構築を担当することも。本プロジェクトでは、PMを担当。
-

N.N
- PROFILE
- 専門学校の説明会をきっかけに、2002年KTSへ入社。職種はインフラエンジニアであり、本プロジェクトではPLを担当。
-

M.S
- PROFILE
- 2002年入社。ネットワーク担当として、PMから保守まで幅広く担当する。本プロジェクトでは、ネットワーク設計、ファシリティ設計担当をしながら、PLを兼務。
-

M.M
- PROFILE
- 2017年入社。オープン系のエンジニアであり、本プロジェクトではストレージを担当。
INTRODUCTION
IaaSサービスを提供するお客様の、とある製品シリーズにおける新基盤構築。過去から継続で取引のあるお客様ではあったものの、サーバー台数が200台と非常に大規模なプロジェクトであったことや、スケジュールの短さなど、柔軟な対応が求められたプロジェクトでもありました。重要だったのは、社内外のコミュニケーションだったとチームは振り返ります。
サーバー200台。品質は最上。
難題をいかにやりきるか。
M.N) 今回お話したいプロジェクトは、お客様が、エンドユーザーへ提供しているIaaSのサービスシリーズ。今回は同じシリーズの中の、新製品基盤を構築するプロジェクトでしたが、KTSは以前より同シリーズの基盤構築を任せてもらっていました。つまり引き続きのご依頼。プロジェクトメンバーも、以前から携わっている人ばかりです。
N.N) 新規の基盤構築ではありましたが、何度も担当させていただいているシリーズ。率直に言えばまったく初めての難しさはなかったように思います。
M.M) ただしサーバーの設置台数が桁違いに多かったことや、これまでよりもお客様の要望が高くなったことなどには、難しさを感じました。
N.N) そうですね。KTSが担当する通常のプロジェクトなら、サーバーの台数は30台でも多いくらい。しかし今回は200台のサーバーを設置する必要がありました。
M.S) 元々がエンドユーザー数も多く大規模な基盤でしたし、それを更新して新規基盤に移行するのでより多くのサーバーが必要になったんですよね。そこで今回は初めて、ネットワークは協力会社に依頼をする形をとりました。
M.M) お客様の要望レベルが高かったことについてはどうですか?
M.N) もちろん到底できない無茶を言われるお客様ではありません。元々築いてきた関係性もある。一方で、品質では常に最上を目指すことも求められました。
M.S) たとえば「どんな障害にも1秒以内に復旧対応できるようにしてほしい」とオーダーがありました。このあたりはネットワークが重要になります。そういったオーダーへどのように対応するか。どうすればできるか。お客様とのコミュニケーションも重要でしたね。
N.N) サーバーの台数の多さでは協力会社と、より高い品質を目指すためにはお客様と。いずれもコミュニケーションが重要だったプロジェクトだということですね。ではその難しさを乗り越えるにあたり、重要だったことや印象的だったことについて。それぞれの視点で話してみましょう。

お客様の要望をどれだけ汲み取るか。
協力パートナーの舵取りはKTSの大事な役割。
M.N) 協力会社さんとのやりとりでは、主にM.Sさんが尽力してくださいましたよね。
N.N) M.Sさんはネットワークとファシリティをお願いしていましたが、ほとんどPLのような動きをしていただいたと思います。協力会社さんとのやりとりはどのような大変さがありましたか?
M.S) 初めてネットワーク担当をともにする会社さんだったこともあり、指示出しや前提の共有が難しかったですね。お客様が当たり前だと思っていることが、協力会社さんにとっては当たり前じゃない。たとえば以前からお客様のことをよく知っている我々なら「このお客様だったらこの機能は使わない」と考え、必要ない機能を止めることができる。しかし協力会社さんにとってそれがデフォルトで動作している機能は止めないんです。どの機能が、なぜ要らないのか。私たちが丁寧に説明する必要がある。ちょっとしたコミュニケーションの行き違いを根気よく修正しなければなりませんでした。
M.M) KTSはマルチベンダーを謳っていますし、幅広く様々な会社さんから最適なところを選んで取引することができる。一方で、初めての会社さんの場合はイチから関係づくりを行う大変さがありますよね。
N.N) 品質にこだわるお客様なので、「他社での稼働実績や安定稼働状況など様々な情報を踏まえて、最適な製品ややり方を吟味してほしい」というオーダーをいただいていました。しかしそこをきちんと汲まずにいると、自然とメーカーさんは「最新製品=いいもの」としてオススメくださるんですよね。間にいる我々の舵取りの大切さを、改めて実感しました。

お客様と「ともに」作業することが、
学びや振り返りのきっかけに。
M.M) お客様の要望レベルが高い点も大変でした。使用するのは、お客様のお客様、つまりエンドユーザーです。高い品質を求められるのもある種当たり前ではあったのかなと。プロジェクト途中での大幅な変更もあり、臨機応変さが求められるプロジェクトでした。
N.N) 臨機応変さは、KTSの強みでもある。十分に活かせたのがよかったのではないでしょうか。よく私たちは「グレーゾーン」「お客様外守備」と言ったりしますが、つまりそれまで見落とされていたり新しく発生したりしたタスクを積極的に引き受けます。「やっときますよ!」と言えるかどうか。本当にちょっとしたことですが、これができるとその後の信頼を得られるんです。
M.N) PMとして、お客様とのコミュニケーションには気を配りました。ちょっとしたことでも電話をするとかね。お客様が今どのような状態なのか、声のトーンなどからもわかることがあります。様子を察して先回りしながら動くことが大切でした。
M.S) お客様と自分たちの領域を線引きせず、ゴールへ向けて一緒に作業をする感覚を持っているんですよね。それが信頼関係につながる。だからKTSは、昔から長い関係のお客様が多いのだと思います。
M.M) M.Sさんは、お客様の検証環境に一緒に入って、テスト作業をしていましたよね。
M.S) そう。お客様の一員のような動きができました。お客様の検証環境で本番環境に向けたテストを、お客様と一緒に実施できたことは、個人的にも勉強になりましたよ。
M.N) どんな学びがあったのでしょうか?
M.S) 本番環境を忠実に再現された検証環境上で多種多様なテストを実施することで、より精度の高いテストが行えました。
そのテスト結果を本番環境にも反映させることで、本番環境に与える影響を最小限にとどめる対応を行うことができたので、本番環境を想定したテスト条件の検討やテスト精度を高めることの重要性を再認識しました。
M.M) テストは私もいい経験をさせていただきました。やるべきことが多い分、緊張感があった。しかしその緊張感、ちゃんと普段から感じられていただろうか?と思ったんです。いつの間にか仕事が、同じ作業や惰性になってはいないか。自らの仕事の姿勢を、改めて振り返るきっかけをもらった気がしています。

先輩にやってもらった分、自分も守備範囲外に出てみよう。
N.N) 協力会社さんとのコミュニケーション、お客様とのコミュニケーションの話をしてきましたが、社内プロジェクトチームのコミュニケーションも大切でしたね。やることが多い分、それぞれの状況を上手く共有できずに遅れをとれば、それは致命傷になる。社内掲示板を活用し、リアルタイムでの状況確認を怠りませんでした。
M.N) 遠慮なく自分の状況を発信したり、チームメンバーを気にかけたり。難しいことだけれども、思い切って踏み込むことが大切だと思いました。属人的になって状況がわからないのが一番よくない。
M.S) そうですね。KTSの社員は責任感の強い人が多く、それはいいことだと思いますが、裏を返せば抱え込んでしまうことにつながります。お客様とのグレーゾーンも任せてもらうのと同じくらい、チームメンバー同士でも、それぞれの守備範囲が重なるくらいちょっと広めにカバーしにいくのが大事ですよね。
M.M) 昔から先輩たちにそうやって助けてもらってきたから、自分も守備範囲外に出ていって、誰かを助けようと思えるのかもしれないですね。先輩の背中を見て育ってきたというか。それがKTSでは脈々と受け継がれている。
M.N) 私たちの強みを、きちんと活かせているのかもしれません。私たちの拠点は、どの職種もワンフロアで同じオフィスにいる。物理的な壁がないので、ちょっとしたことでもすぐ話しかけに行ってコミュニケーションをとる文化があります。社内の円滑なコミュニケーション文化が、結局お客様の利益にもつながっているのではないでしょうか。
N.N) 風通しのよさが強み。他の企業が一朝一夕では真似できない強みを持っているんですよね。今回のプロジェクトは一段落していますが、来年以降もまた、同じお客様の新製品プロジェクトが動き出しそうなところ。次のプロジェクトでも、私たちの強みを発揮しながら技術を提供していきましょう。

- PREVIOUS 前の記事
- NEXT 次の記事
- 記事一覧へ